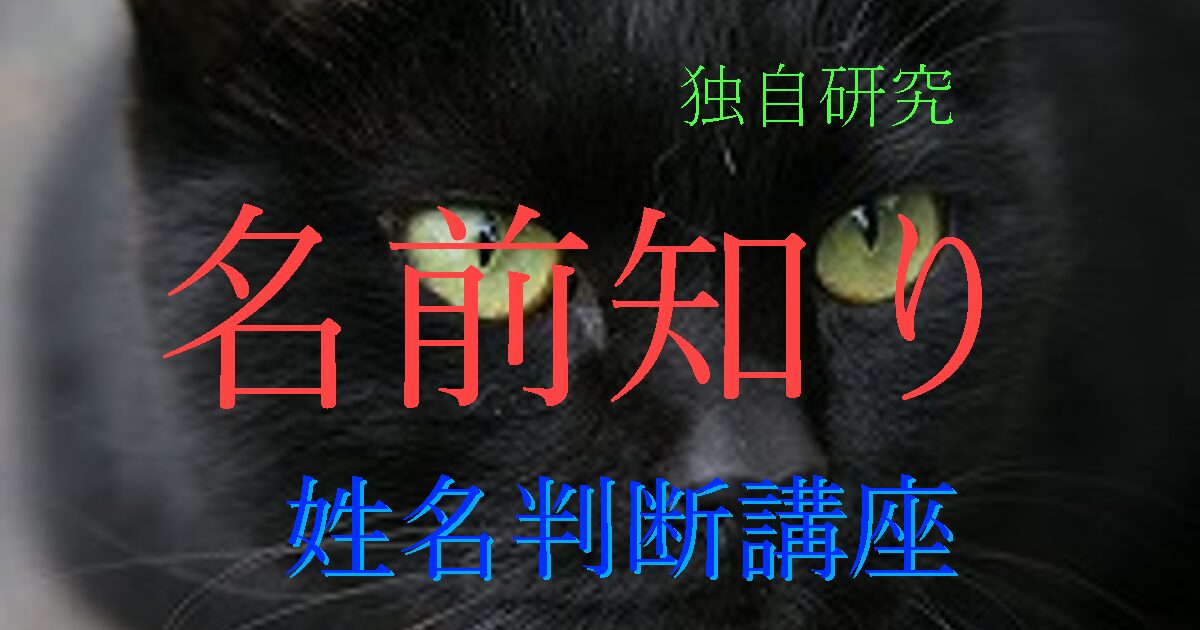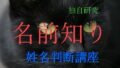アフィリエイト広告を利用しています
人運21を持つ人は、高度な論理的思考を持ち、いかにも仕事ができる、というタイプです。
その人運21を持つ人への対処法を、考えてみようという企画です。
ここでは、「名前知り」の観点から、人運21を持つ人への対処法を、考えます。
人運21を持つ人の基本性質
人運の21は、頭が良く、特に論理的思考力が優れています。
冷静に分析することができるので、緻密な計画を練ることができます。
リーダーシップに優れているので、社会的な評価を得ることができ、人の上に立つことができます。
ですが、完全主義的な傾向があり、そのため慎重になりすぎるので、注意が必要です。
重箱の隅を楊枝でほじくる、ような事をしていると、運はどんどん下降していきます。
また、金銭が絡むと手段を選ばないことがあるので、気を付けましょう。
人運21を持つ人へのNGワード
人運21を持つ人は、高度な論理的思考を持っています。
なので、論理的に説明できない人には、耳を傾けません。
また、順序立てて説明するか、根拠を明示する必要があります。
NGワードの例
(1)なんとなく○○と思う。
(2)たぶん○○です。
もし同僚なら
人運21を持つ人は、仕事ができる人が多いので、是非とも味方にしたいのですが、「名前知り」の人には、とてもハードルが高いと、思われます。
さらに、人運21を持つ人は、人を信用していないところがあり、相談などには乗ってくれない人、が多いです。
だから、相談などはしたくない相手ですが、高い論理的思考は、あてにしたいところです。
なので、もし、相談をしたいのなら、順序立てて説明する必要があります。
そのときは、数字などで、根拠を示すのも良いでしょう。
また、数字を示すときは、ちゃんとした数字を出す必要があります。
だいたい○○付近の値、というような、中途半端な数字では、納得しないでしょう。
なお、不安に思っていること、や、漠然とした問題、を相談しても、一蹴されることでしょう。
もし上司なら
人運21を持つ人は、仕事ができるので、出世することでしょう。
なので、上司として接することが多いと思われます。
基本的には、順序立てて説明できないと、相手にされないです。
その辺は、同僚の場合と同じです。
ここでは、気を付けなければならない点を、指摘します。
それは、目的の為には手段を選ばない、という点です。
他人の感情に寄り添うようなことは無いので、人員整理などは、簡単にできます。
そして、感情に訴えても、聞き入れることは無いでしょう。
また、部下の手柄を横取りする、こともできるので、注意しましょう。
それを防ぐには、予め、誰の案なのかを明示する必要、があります。
もし対戦するなら
人運21を持つ人は、論理的思考が発達しているので、対戦するときは、非常に手ごわいことでしょう。
それでも、戦わなくてはならないことも、あるでしょう。
ここでは、どのように戦うのが良いかを考えてみます。
欠点と言える点は
- 慎重で石橋を叩いて渡るところがある
- 重箱の隅を楊枝でほじくるように追及する
ということぐらいでしょうか。
その点から見れば、優柔不断さがある、と言えるのではないでしょうか。
ならば、優柔不断さを引き出すように対処できれば、十分に勝機があるはずです。
細かい問題点を次から次へと指摘する
それには、細かい問題点を次から次へと指摘する方法、が良いと思われます。
なぜなら、普段から、重箱の隅を楊枝でほじくるように追及する癖がある、からです。
なので、同じように問題点を次から次へと指摘されれば、対処するしかなくなる訳です。
そうすれば、もともと石橋を叩いて渡るようなところがあるので、なおさら決断できなくなるでしょう。
あとは、決断できない人というレッテルを貼れば良いわけです。
ただ、国会中継を見ているようで気分が悪い、かもしれませんが。
でも、実際に国会では、有効だったようです。
誰とは言いませんが。
まとめ
人運21を持つ人は、高度な論理的思考を持っているので、対処法を間違えないようにしましょう。
ただ、石橋を叩いて渡る様な慎重さがあるので、付け入るスキはあります。
もし、対戦するなら、次から次へと問題点を指摘する方法が有効です。
味方に付けたいのなら、優柔不断さを出さないように工夫する必要があります。
- はじめに
人見知りを超えるにはどうする方法があるかを考えてみました。
- 対処法避けられない人間関係の対処法を人運別に考えてみました
「名前知り」の観点から人運21を持つ人への対処方法を考えてみました。
「名前知り」の観点から人運13を持つ人への対処方法を考えてみました。
「名前知り」の観点から人運16を持つ人への対処方法を考えてみました。
「名前知り」の観点から人運15を持つ人への対処方法を考えてみました。
「名前知り」の観点から人運11を持つ人への対処方法を考えてみました。
- 仕事運
- 圧力に抗う
人間生活における様々な圧力に抗う手段として姓名判断を駆使する方法を考えてみました。
- 休憩中「名前知り」から少し離れてみようかと
筆者紹介

白と黒のぶちネコ
独学で技能を習得することが趣味。
知識や技能は使用してこそ意味があり、公開してこそ価値がある、という考えに至りブログにて公開することを決めた。