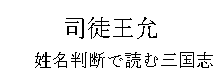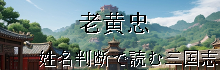明治時代に日本に侵入して、おもに東日本で繁殖している、マルバフジバカマに関する雑学を、紹介します。
ここでは、マルバフジバカマに関する雑学を、紹介します。
明治時代に日本に来た外来植物
マルバフジバカマは、1896年(明治29年)に、日本に持ち込まれたとされる外来植物です。
元々は、観賞用に持ち込まれたのですが、いつしか、漏れ出て、現在は北海道から近畿地方まで生息域を広げています。
最初は、神奈川県箱根町付近に持ち込んだらしいのですが、北への進出が早いのに、西への進出が遅いのは、暑さをやや苦手とするようです。
また、薄暗く湿った環境を好むようです。
花を咲かせる時期は10月で、白く小さな花を20ぐらい咲かせます。
もともと観賞用なので、きれいな花を咲かせます。
毒を持っているので、誤って摂取すると、最悪死亡します。
本当の脅威は
別に、毒を持っている植物は、普通にいるので、そのぐらいでは雑学と呼べるものではありません。
この植物の危険性は、直接摂取しなくても、中毒になることがあるというところです。
この植物は毒があるので、シカは食べません。
しかし、何故かウシは、食べます。
食べて中毒になると、多量のよだれ(もともとウシはよだれを垂らすが尋常でない量のよだれを垂らす)を垂らし、身体をだるそうにし、やがて呼吸困難になるようです。
その状態に気付かずに、ウシから搾乳したミルクを、人間が摂取すると、人間が中毒になってしまい死亡することがあります。
この中毒を、ミルク病と呼びます。
実際に19世紀の米国では、ミルク病によって、多数の死者がでました。
かの、リンカーン大統領の母も、このミルク病で死去した、という話があります。
同時の科学技術では、原因の究明までに、数十年要しました。
安心して牛乳を飲んでください
現在の日本では、徹底した品質の管理のもと、そのようなことが、起きることはありません。
市販の牛乳に、この植物の毒が混入する可能性は、ありません。
なので、安心して牛乳を飲むことができます。
安全な牛乳は、普段からの管理が重要であることは、言うまでもありません。
生息域を広げている
このマルバフジバカマをシカは、食べません。
シカは、うまい具合にこの植物を避けて食べます。
そして、マルバフジバカマだけが残ります。
このことが、生息域を広げる原因になっています。
実際に岩手県では、こうして生息域を広げた、マルバフジバカマが大繁殖しているようです。
もし気になるのなら
この植物の毒は、中程度の毒とされています。
毒の強さだけなら、トリカブトやドクゼリの方がよっぽど強いとされています。
ですが、摂取すれば、人間が死亡する毒です。
なので、無分別に植物を食べるのは、とても危険なことです。
しかし、子供は無意識に口にする癖が、あります。
だから、注意する必要があります。
広告です
一番の対処方法は、除草することです。
専門の業者に依頼するのが、最も適した方法です。
なぜなら、触れるだけで、かぶれてしまう草があるからです。
植物は、生き残るために、ありとあらゆる方法を身に付けました。
触ったらかぶれる、というのは、植物の世界では、生ぬるい方法です。
なので、危険な処理は、専門の業者に任せましょう。
雑学としてみるなら
植物の雑学は、もっとあります。
例えば、媚薬となった植物とか、ライオンを殺す草なども、雑学として面白いでしょう。
広告です
このような植物の雑学が、載っている書籍を紹介します。
 | 面白くて眠れなくなる植物学 (PHP文庫) [ 稲垣 栄洋 ] 価格:814円 |
 | 怖くて眠れなくなる植物学 (PHP文庫) [ 稲垣 栄洋 ] 価格:814円 |
まとめ
マルバフジバカマは、気を付けなければならない、植物と言えます。
ミルク病は、その最たる例です。
ですが、現代の日本では、気にする必要は、無いと言えます。
野良のウシ(?)のミルクを飲むときは、注意しましょう。
参考文献
国立環境研究所(2024年6月11日閲覧)https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/81020.html
筆者紹介

白と黒のぶちネコ
独学で技能を習得することが趣味。
知識や技能は使用してこそ意味があり、公開してこそ価値がある、という考えに至りブログにて公開することを決めた。